| 後期楽焼(第二次大本事件後) | |
| 製作期間 | 1年5カ月 |
| 始 | 昭和19年(1944)年12月末 御年73歳 |
| 終 | 昭和21年(1946)年3月 御年74歳 |
| 製作数 | 耀盌以外の作品(水差など)も含めて約5千点 |

後期楽焼
<耀盌の製作>
昭和19(1944)年12月29日〜昭和21(1946)年3月25日
「もう一ぺん造る」
「先生(王仁三郎聖師)は楽焼を非常に大切にされ、倉一杯に2千以上もしまっておられましたが…(第二次大本事件後、聖地に)7年ぶりに帰ってみますと、一つ残らず粉々にわられておりまして、そのときの先生の子供のような悲しそうな顔が目に見えます。それでも、愚痴もこぼさず、恨みごと一つ言うでなく、ただ『もう一ぺん造る』とだけ言われたのには感心させられました。
(聖師)74歳の冬から2度目の楽焼が始まりました。
やり出されますと、あれが三昧というのでしょうか、明けても暮れても楽焼のことばかりで、私らの話さえろくに耳にはいらんようでした。工房から帰るといつもくたぶれて、力がぬけてヒョロヒョロですのに、『えらい』とでも言おうもんなら内の者が心配して止めると困るので、疲れた顔をごまかそうと思うてか、手拭いで顔ばかり拭いておられました。
しかし、75にもなる先生の体を心配して、私や娘たちがやかましく言うて一時は止めてもらいましたが、それでも眼をぬすんではこっそり行って造ってられましたし、またよくよく出られん時には、どうもやりとうてたまらんというふうで、色紙にせっせと茶わんの絵を描いて楽しんでおられました」
出口すみこ二代教主(談)

全霊を込められた《土》ひねり
「父(聖師)の耀盌は、陶車によらず手造りで、父の全霊を指先に集中して、一指、一指から、土の一塊一塊に念力を移しつつ、その一瞬一瞬に、地の上に神の国をさだめまつる祈りをこめて、たんねんに形造ったものです。盌体の持つ豊かな広がり、神界の輝きそのままの色彩、天象の紋理をひめたこまやかな刺孔(簓であけられた穴)、たしかに父の祈りは生き生きとしています」
出口直日三代教主(談)
苦心された土
聖師が楽焼に使用された土は、主として亀岡の手近の溜池の土や天恩郷神苑の土などであった。耀盌の独特の卵色の土味は、天恩郷の土から引き出された効果である。しかしそのご作陶の影には大変なご苦労があった。
「亀岡のはどこのを取ってきてもパサパサで、瓦くらいにしかならぬ粗末なものです。とても普通の陶器屋の手をつけるような代物ではありません。それで京都の土(滋賀県信楽より産出)を持ってきてつなぎに一割くらい混ぜましたが、それでも腰が弱くて難儀しました。表面を白い土で化粧して、やっと抱かせて焼きました。聖師さまは『それ、ヘタルヘタル』と言っては苦心されたものです。」
佐々木松楽氏(談)
こうした困難な条件のなか、気をつめ、精神力を手先に集中して土にあたられるため、途中で訪問者があると、グニャグニャにつぶれてしまった。よって作業場へは、お手伝い4人のほか、だれも立ち入ることを許されなかった。

最悪の条件下で
初窯は、昭和19(1944)年12月の年の暮れで、日本は戦争の真っただ中にあり、原料店はどこも扉を閉めていた。
「土質が悪いばかりでなく、戦時中のことですから、原料屋はすべて店を閉めているので一斤(約600㌘)の絵具、一束の薪さえ手に入れるのが容易のわざではありません。私はアチコチ閉鎖している原料屋を探し回っては、売れ残りの原料をかき集めたものです。土もいっぺんに10貫目(約38㌔㌘)ほどずつ担いでは、京都から満員の汽車に乗って帰りました。その頃は第一、切符も自由に買えなかったのです。
絵具は私の買いだめたもの(約10数年分。すべて1年余の耀盌制作に使用)がありましたが、金沢や九州の有田の信者さんから送ってきたり、全国から熱心なご奉仕がありました。こうした最悪の条件を克服して、あれだけのお作品が出来上がったということを考えねばなりません」
佐々木松楽氏(談)
《耀盌》独特の手法
陽光を想わせる刻線、星天のように見える孔



小さな穴は、この手法のために特別に作ったササラ様のもので(写真下)、一念一突、聖師が「かんながらたまちはえませ」の言霊を込められながら打たれた。
「簓(ささら)」= 竹の先を細かく割って束ねたもので、長さ30㎝くらい。かつては民俗芸能の楽器の一種であったり、洗浄器具としてタワシの用も担っていたこともあった。

惜しげもなく差し上げられた
「(聖師は)窯出しの日はいかにもうれしそうに、車(リヤカー)に焼けた茶盌を積んで引っぱらせ、まるで桃太郎のがいせんのような格好で帰ってこられ、その茶盌の一つ一つを取り上げては眺め、
『この楽焼一つ作るのにも二千遍のかんながら(惟神)の言霊をこめ、火と水と土と、それにわしの霊の力が入ってできたんや。そやからこれがほんまの玉やで、いまお前らわろうとるが、いまに宝になるのや』
と自慢しておられましたが、ともかく先生(聖師)が一心こめて真剣になってやられたのですから、尊いものができてるのやろうと思うてます。
そのように命をこめて造られた楽焼でしたが、先生はそばに人が来ると惜しげもなくやられました。作るほかに、自分の作品を見てもらうのがまた楽しみやったんでしょう」
出口すみこ二代教主(談)
昭和21(1946)年3月までの1年3カ月、茶盌だけでも3千個以上を生み出された。戦時下の暗く重苦しい時代に、えんじ、瑠璃、黄色、緑、いろとりどりの茶盌は、下げられた信徒にとって、未来への希望をみる思いだったかもしれない。
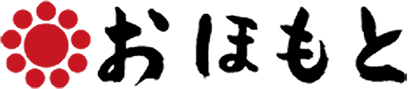





親の代からの陶工。戦争中に京都市から亀岡市下矢田町へと移住。この宅に築かれた楽焼窯が耀盌制作の現場となった。松楽氏も一貫して制作に奉仕。また、同氏の父(楽吉氏。初代松楽)は聖師の前期楽茶盌制作に仕えた。