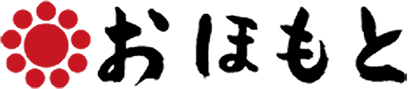令和3(2021)年には、出口王仁三郎聖師が大正10年10月18日に『霊界物語』のご口述を開始して100年の佳節を迎えました。出口王仁三郎聖師は霊界物語について救世の教典であると示している他、「いくたびも繰返し見よ物語神秘のかぎはかくされてあり」「のあらむ限りは人の世の光とならむこの物語」などのお歌を数多く残しています。
霊界物語 第1巻 霊主体従 子の巻 序から 出口王仁三郎
この『霊界物語』は、天地剖判(てんちぼうはん)の初めより天の岩戸開き後、神素盞嗚命(かむすさのおのみこと)が地球上に跋扈跳梁(ばっこちょうりょう)せる八岐大蛇(やまたのおろち)を寸断し、つひに叢雲宝剣(むらくものほうけん)をえて天祖(てんそ)に奉り、至誠を天地に表はし五六七神政(みろくしんせい)の成就、松の世を再建し、国祖を地上霊界の主宰神(しゅさいしん)たらしめたまひし太古の神世の物語および霊界探検の大要を略述し、苦(く)集(しゅう)滅(めつ)道(どう)を説き、道(どう)法(ほう)礼(れい)節(せつ)を開示せしものにして、決して現界の事象にたいし、偶意的に編述せしものにあらず。されど神界幽界の出来事は、古今東西の区別なく現界に現はれ来ることも、あながち否(いな)み難(がたき)きは事実にして、単に神幽両界の事のみと解し等閑(とうかん)に附(ふ)せず、これによりて心魂を清め言行を改め、霊主体従の本旨を実行されむことを希望す。読者諸氏のうちには、諸神の御活動にたいし、一字か二字、神名のわが姓名に似たる文字ありとして、ただちに自己の過去における霊的活動なりと、速解(そくかい)される傾向ありと聞く。実に謝れるの甚だしきものといふべし。切に注意を乞ふ次第なり。
大正十年十月廿日午後一時
於松雲閣 瑞月 出口王仁三郎誌
大本史点描:我は人の心の奥深く 真の殿堂を築くのである
- 「霊界物語」の筆録者の一人である加藤明子さんが、筆録に関するご自身の体験談を、昭和9年11月号の「神の国」に執筆されたものです。
もはや12年になります。隙行く駒の足並み、早いことにはただ驚かされるばかりです。編集課よりのご希望によりまして、『霊界物語』ご口述当時の記憶をたどって、思い出を書かせていただこうと存じますが、往事茫として夢の如く、折から手元に当時の日記もないので、ほんの思い出づるままを少しばかり書かせていただくことに致します。
大正10年の10月15日の午後3時ごろ、聖師さま(当時は大先生と申し上げておりました)よりお使いがあって、ちょっと来てくれとの事で、大本に行きますと、
『すこし書きたいものがあるのだが、王仁が、筆を執るわけにゆかぬので書いてもらいたい、外山さんと、あんたと、ほかに二人ばかりの人が入用なのだ』
とこんなようなお話で、並松の松雲閣でご口述が始まることになったのです。初めは3冊ばかり書いてもらったらよいのだとおっしゃていました。
いよいよご口述が始まったのは、10月18日でありまして、外山豊次さんの筆録「天使の来迎」という章からでありまして、その時、桜井八州雄、谷口雅治の二氏が参加されて、4人の筆録者が代わる代わるご用を承ることになりました。
松雲閣に移られても、なかなか口述は始まらず、余程ご苦心のように見受けられました。17日の夕方うつうつと眠られていましたが、ふと目を覚まされて、『今教祖さまが、それ今お前の座ってかるところに立たれて梅の杖を持って畳を打ちたたきつつご機嫌が悪いご様子なので、本宮山破壊などの出来事について怒っていらっしゃるのだと思い、おわびを申し上げると、首を左右に打ちふってそうではないという意を示されるので、物語のご神命をうけながら日をのばしていたのでそれかと気がつき、物語をすぐ始めますと申し上げると、口を四角にしてニコッと笑われ、そのまま消えてしまわれた、いよいよ始めねばならぬ』
とこんなことを仰せられて、翌18日からいよいよ着されたのでした。初めは聖師さまも余程お出しになるのがお苦しそうでした。筆者が慣れぬので、すらすらとは書けぬのがその一つですが、後より承りますと、悪霊の大妨害があってなかなか出てこなかったのだとのことでした。
この物語は寝物語だとおっしゃって、横にならなければ出てこないのですが、天地剖判の章を口述される時だけは、紋服に袴をつけられて端座して口述されました。
初めの程は鉛筆をもって半紙に書き、それを原稿用紙に清書し直しておりました。26巻ころからは、いったん書いて清書しなおすことを神さまが嫌われるから、すぐ原稿用紙に書けとのことで、原稿用紙にベタ書きにするようになりました。このころからご口述は非常の速力をもって進みまして、とうとうと水の流れるがごとく、慣れない者では到底追いつかないようになってきましたので、筆録者も自然一定の人に定まってしまいましたが、初めはこの物語がどういうふうに出るかということをかなりたくさんの人々に知らせたいというお考えであったらしく、多くの人々が参加するようになりまして、33人の人々が関係しております。
もちろん1章だけ書かせていただいた者もあり、2、3章ぐらいおかげを頂いた者もあります。単に筆録の現状のみではなく、ご口述の現場にもはべることを許されたのでした。これは局外者の目から見れば事実とは信じられぬような出来事を実際に見せておく必要上から、神さまが許されたもので、後に至っては筆録者のほかの者が立ち入ることは厳禁されるようになりました。また全く、ご口述者と筆録者との呼吸がピタリあって、間髪を入れるの余地がなく、動くはお口と手、サラサラと原稿紙の上を走るペンの音のみ、人なく我なく森羅万象のすべてが消滅している境地になった時、だれかが入ってくるようなことがあれば、その物音にハーモニーがやぶれて、筆録者は瞬く間に、4、5行くらいは遅れてしまうので、非常に困るのでした。
光をもった小さな玉が…
私はこの機会においてご口述のありさまをちょっと記させていただきたいと思います。
聖師さまは、まずお床の上、あるいは寝台に横臥されます。おタバコのセットと、お茶盆が前におかれてあるだけで、なんらの参考書もノートも用意されてはおりません。かくておタバコを一服か二服か召し上がるうちに、お口がほどけて、
『大国常立の尊の御力によりて天地はここに剖判し、太陽、太陰、大地の分担神が定まった』
というふうに口をついて出づるまま述べ立てられる。筆録者は一言も漏らさじと筆をふるいます。一日口述の量は200字詰めの原稿用紙に400ページないし500ページであります。1冊が2日で出来上がった時は1日600ページ以上口述されました。もっとも一罫をおきに書いているのですから実数は200ページから250ページであります。三日間に三百五、六十ページの霊界物語が一冊完成するわけです。
さてご口述の調子は早い時になると素晴らしく速く、早口の人が話しする程度でして、速記ならでは到底取れないような時もありますが、そういう時はまるで夢中で筆を飛ばします。それでも叶わぬくらい早くなって五行、六行くらいも遅れる時があります。他の筆録者の体験はどうか知りませんが、かかる時私は思わず心の中で『神さま助けてください』と叫びます。そうすると、原稿紙の上にちょうどダイヤモンドと同じ光をもった小さな玉がパッパッとでてきます。自分ではほとんど何を書いたか覚えぬような時でもちゃんと間違わずに書けているのに自分ながら驚いたことが幾たびあるか分かりません。一番口の速いのは高姫さんで、豆がはじけるように述べたてるのに反して、初稚姫さまなどはおちついてしとやかなゆっくりしたお言葉です。だから初稚姫さまが物語中に出てこられると、筆録者はホッとひと息つきます。かくて書きあげたものはすぐ他の人が読みます。それを聞いておられて、違ったところがあれば、そこは違っておると仮名一字の間違いでも厳重に訂正されます。ですから筆録者の方では他人が読んで分かる程度に書かねばならぬのですからかなり苦心いたします。だけれども調子は遅いよりむしろ早い方が書きよいので、何かはかの事を考える余裕があるとかえって遅れるので、考える余地がないくらいの速さで、ハーモニーがよく取れた時が一番よいのです。漢字交じり文で書くのですが、全く忘れているような文字でもその時は押し出すように出てきます。かくて口述される方も筆録者も全く忘我の境地に置かれております。
ツルツルと水の流れるがごとくに出てくるのですが、途中で分からない事などがあっても問い返すわけにはいかないので、問い返すその瞬間バタリとご口述は止まってしまいます。そしてしばらくは出なくなってしまいますので、どんなにわからない事があっても問い返すわけにはいかず、済んでしまってから、あのところは分かりませんでしたから、もう一度言っていただきたいとお願いすると、『王仁が言うているのではない、神さまが申されるのである、後から聞いても分かるものか』と申される。『その上一言でもかき漏らすと取り返しがつかぬ、神には二言がないから』と申される。かくなると人間業では到底できないので、ひたすら神さまにお願いしてご神助を仰ぐほかないのでありました。
七十二巻をものされる中には、種々の出来事もありますが、いずれ期を待ってゆっくり書かせていただくことにいたしましょう。が、この物語がいかに霊界に感応していくかということについて、少し述べさせていただきます。
ご神殿の破壊される音を聞きつつ
言い置きにも書き置きにもないことを示すのであるとお筆先にありますが、全く善悪にかかわらず神界、霊界のありさまを暴露されるのですから、兇党界には大恐慌をおこしたとみえて妨害につぐ妨害があって、その度聖師さまはもちろん筆録者一同もずいぶんひどい目にあったことも一切ならずでして、ある時物語に言霊別の神さまが毒殺されんとする場面が出てきましたが、そのご口述のあった日、聖師さまはじめ十六人の人が吐いたり、下したりして大騒ぎになったことがありました。
また私は、松雲閣の記録場に入って行くことがとても苦しく、門を入ることは槍襖の中を歩むような心地で、屠所の羊の歩を運んだことが、幾月日だか分からないのでした。某霊覚者が経験を語って、霊眼で見れば正に槍のふすまであると申しておりました。悪霊は自分の素性を霊界物語によって暴露されるのを非常におそれて極力妨害したのであるとか承りました。筆録者すらかくのごとしですから、聖師さまのお悩みはまた格別で、筆紙につくせぬ種々の出来事がありました。皆人間を使っての妨害でありまして、使われている本人はもちろんそれを自覚してはおりませんでした。
物語の初まったころ、大本は神のご試練の鞭がいや茂く下りつつあった時で、ことに天のご三体の大神さまを斎きまつるため、幾十万金を投じて建立した本宮山のご神殿が、明治初年ごろに定められた大政官令にふれたとあって破壊されるという騒ぎ。
この破壊の槌の音、メキメキとなる柱の倒れる音、木の切られる音を聞きつつ、平然としてその山の下にある松雲閣で、『形のあるものは必ず壊れる時が来る、我は人の心の奥深く真の殿堂を築くのである』とおっしゃって、せつせつと物語を続けられたのでしたが、私ども人間の身としてはその斧の音、槌の響きは、三十三間堂の柳ではないが、胸にこたえて堪えがたさを痛切に感じつつ筆を走らせておりました。
(「神の国」昭和9年11月号から)