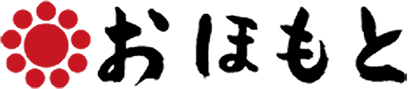「清泉(せみ)の小川を」(昭和57年6月5日、出口直日三代教主)
出典:教団機関誌「おほもと」昭和57年7月号、天声社刊『教主御教示集―出口直日三代教主』
この文章は、三代教主自身の筆により、大本機関誌に発表されたものです。教団にとって最も重要な
教主継承者・教嗣の変更について、どのような経緯で三代教主が最終の決断にいたったのかが、詳述
されています。なお( )内の注釈は編者によるもの。
大本は開祖さまのお筆先によりまして、世継ぎのことは二代三代と明示され、後々も、代々女でなければならないと定められています。申すまでもなく、この定めは、この教団にとりまして変えることのできない神律であります。この中の事情がどう変わりましょうと、世間の状勢がどう動きましょうとも、これだけは曲げることはできません。
三代から四代へ、四代から五代へと、その時の教主が、世継ぎにもっともふさわしいものを神さまのご摂理のもとに、代々立てることになっています。
女の中から世継ぎを立てることには、いろいろ考えられるでしょうが、開祖さま聖師さまの血統を、もっとも清く間違いなく伝えて栄えてゆくためには一ばんよいさだめであるとおもいます。
さて、大本四代の世継ぎとしては、私たちの長女の直美が早くから予定されていました。父(出口王仁三郎聖師)も母(出口すみこ二代教主)も、直美の生まれた時から四代の世継ぎとして大きな期待をかけていました。私も、直美は幼少のころから――この子は生まれながらにものの本質をみることができる――と世継ぎに決めてまいりました。
直美の長女直子が学府を出て縁談がもちあがりました時、――教団における直美の立場を明らかにしておかなければ――という声がおこり、うちまるさん(出口うちまる〔宇知麿〕氏。当時の代表役員。三代教主の義弟)たちが教主継承規範を成文し、教則の一部改正までおこない、直美を後継者として発表したことにも、私は“こんなことまでしなくても、もともと決まっていることなのに……”なんという信の浅い人たちばかりだろう! となげいたものです。
その直美の世継ぎについて、ここに考え直そうというのですから、私としましては悲痛なおもいにならざるを得ません。
ずっと以前のこと、どれくらいの期間ですか、直美は教主になることをのぞまなかったころがあるようです。束縛を感じてか、自由な別の生き方にあこがれたのか、こんなことがありました。
朝陽舘(亀岡天恩郷の教主公館)で私が急性盲腸炎になり、かかりつけの医者が、このままでは危ないからすぐ手術をしてもらうよう京都府立病院へ入院手続きをとってくれ、これから出かけようとしているところへ、綾部で私の急を聞いた直美がかけつけてくれ、その時、「お母さん、直美はあとを継がんと書いてほしい」と言って紙と鉛筆をわたしました。
手術をうけるためいそいででかけようとしている私に、そのような書き付けをせがむとは、よほど教主にさせられることを嫌がったのでしょう。私は――直美には後を継がせないでおいてやってください――と走り書きして渡しました。
このときのことを、直美はすっかり忘れていると言います。私は生命にかかわるといわれていた時間のできごとだけに、ハッキリとおぼえています。
私には、直美のあの時の気持ちはよく分かるようにおもわれます。それは私にも、あの時の直美に似たような、教主にたいする嫌悪というよりは一種の抵抗をおぼえていたころがあったからです。
その後いつのころからでしょう。直美のこころに、教主を継がなければと申しわけないとでもいった自覚が芽生えて、しだいにふくらんでまいったようです。娘としての直美は申し分のないよい子で、そのころの私は何の不足もありませんでした。
やがて教嗣(教主継承者)の称号も受けてくれ、私のよき手助けになってつくしてくれました。
それが、少し以前から近ごろにかけて、気懸かりなことがありまして、直美をじっと見てきますと、私は、直美の性格がかわったのではないかとおもうようになりました。それは、直美が生まれながらにもっていた《ものの本質を見る目》がどうかなったのではないかとおもわれたことです。
とは申しましても直美は、私に表だってたてつくというようなことはありません。むしろ私に対しては吾不関(ワレカンセズ)の当たらずさわらずの態度です。にもかかわらずその向こうに、これまでとは異なった何かが感じられました。そうおもっても私は、まるで暖簾(のれん)と腕押しをさせられているようでした。
たしかに直美の目と耳には変化がおこっていました。出口の家に生まれた直美が本来的にもっていた自分の耳と目と口も、今ではまわりの誰かのものに変えられています。
直美は直美で――お母さんは何も知られない、お人好しやからまわりのひとらに騙(だま)されていなさる――と言葉には出しませんがそう思いこんでいるようです。
――教主は誰かにだまされている――と、かりに直美に告げるものがいたとしても、以前の直美であれば、その真偽を立て分けてくれたでしょうに。直美の生まれたころも、今も、母の私は少しも変わっていないのですから。
直美は――私がまわりに騙されている――と言い、私は――直美の目も耳も誰かのものになっている――と言います。まるで滑稽本の一節です。一ツの教団の中では、どちらかがほんとうで、どちらかが嘘となりますと、神さまが、毛筋のよこ幅ほども違いないといわれたお筆先によって、三代に立っている私のいうことを聞いてもらうのが順序というものでしょう。
直美は世間的にもよき妻であり、よき母でもあるといわれ、私もそれを誇りにおもっています。ふつうの家であればそれだけで十分で、直美は仕合わせに暮らしたことでしょう。
しかし直美には、主婦として母としての多忙な日常の上に、教嗣としての生き方がありました。これはよそ目には分からない苦労の多いものです。家庭の中にいてものをみているだけでなく、一段と高い心境に立って広く深くものを見る度量がいります。
ここに一ツの壷があります。この壷のことをよく知るためには、壷の一部だけをみつめていてもよくは分かりません。ことに直美の立場は、壷の全体がみえるところにあって、上下左右をみわたして壷のすべてに触れなければなりません。こうしてこそ空間に存在する壷の本質にも触れることができましょう。
ここしばらくの直美をみていますと、大本のことを自分の家の中からのみみているようです。それでは大本の全容は分かりかねます。
これはまわりのものが、知らずしらずに、直美に教団のほんとうの歩みが分からないように邪魔しているからです。直美のげんざいは、そのことにさえ気付いていないようです。
これには、親としても責任があります。
直美は、終戦の年の四月、まだ十五歳の若さで、異性を見る目も幼く、世のなかのことも知らず、思慮分別もそこそこで、周囲から「またとない良縁だから」とすすめるので、直美自身は進学したい希望をもっていたのを、それも抑えて結婚させられたことが、その後の直美を、時に公私の別までも批判することを忘れ、配偶者(出口栄二氏)への盲目的といってもよいほどの献身となり、それがやがては本来の性格にもおよんでいったようです。
直美の今日には、そのように直美の結婚が大きく影響していることをおもいますとき、母親の私としましては、堪え難いほどの痛みを胸におぼえます。
直美は、聖師さま二代さまの初めての女の内孫として、私たちの長女として生まれたのですから、別に教えられなくても、大本がどういうところかということは肌で感じとっているはずです。それなのに近ごろの直美は、自分の家の中だけで教団をみて、大本の動きを広く受け取ろうとしません。その姿にはハッキリいって配偶者の考え方が原因しています。教団のもつれは、実はここに発しています。それでも私の生きている間は、行き過ぎがあれば、抑えることも、戻すこともでき、ごたごたしながらも、踏みちがえないでゆけますが、私がいなくなれば、後は底無しの泥沼になってしまうより外ありません。直美がげんざいのままでは。
ここに直美の四代継承について、見逃すことのできないもっとも大きな問題がわだかまっていたのです。
審査院を私の直属にし、強化して、ことをすすめるために必要な規程をも作らせ、総局からも離れて、教団全体の動きに審査の目を当てて、教団の歩みが軌道から外れないようにこころを配らせました。
そこへいまいった直美の前途にわだかまっている問題を、重要視しなければならないようになってきました。このことは私が教主就任(昭和27年4月)以来、陰に陽に教団のさわりになってきたものとして、教団の歩みのすべてにからんでいたからです。
いまのうちに、なんとかしてこの問題をさわやかに解決しておかないと、四代継承の前途にもさわるという、私としては好意を秘めてすすめたものでありました。
しかしこれらの好意は、なに一ツむくわれずして、私の期待も空しく、すべては裏目に出るという結果になりました。そのことは(昭和57年)五月五日の挨拶文にももらしていますが、私たちの気持ちとはうらはらにことごとく打ち返され、自らを泥沼に追いこんでゆくという対応ぶりで、そのもっともはなはだしいものが、このたびの告訴事件(昭和56年12月8日、出口栄二氏が京都地裁に提訴)となっています。
それほど大きくもないこの教団の中で、このような争いをまきおこすというのは、どういう気持ちなのでしょう。まったく理解に苦しむものであります。
原告(出口栄二氏)は、教主には何の関係もない訴訟であるといっていますが、被告にされた役員の方々は、私がお願いした方々で、私の決裁を受けて、とりおこなったものばかりであります。私は教則で無答責といって責任をとらなくてもよい立場においてもらい、責任はいっさい役員が受けてくれることになっています。よって役員は私の身代わりになっていてくださるともいえます。
こんな訴えを、私たちの教団の中のものが平気でできるものでしょうか。原告は、実際は親を訴えているのと同じことになりましょう。このようなことを日本の歴史で、かつて聞いたことがありましょうか。
どのような理由があるにしましても、このたびの告訴は、大本にあってはならない恥ずかしい事件であるということはいうまでもありません。
しかも、訴えている内容はどれもみ教えによって解決に向かわなければならならないことばかりです。それができないで告訴にふみきったというのは、み教えの受け取り方が横道にそれているからです。それで、告訴したことにより、社会的には自己の信奉しているみ教えの権威を堕とすことになり、宗教人としては自殺行為にもひとしいことに気がつかないのです。さらには、全国の多くの信者さん方にどれだけ大きなご迷惑をおかけするかも分からなくなっているのです。第一に神さまに申しわけのないことはいうまでもありません。国に法律があり、裁判制度があり、すべての人民の権利が平等に守られているのですから、その恩恵は誰にも与えられています。そのお世話になろうというのであれば、信仰させていただいているものは、信仰人としての清純さと温かさをもって、ものごとをよく見つめた上でお願いするのでなければならないでしょう。でないとお世話してくださる方をさわがせるだけのことになりましょう。
こうしたことは原告(出口栄二氏)にも、原告をとりまく方々にも、やがては、分かってもらえることを念じていました。
ことに直美は他の方とちがって、告訴のとり下げを働きかけてくれるものとのぞんでいました。さいきん直美の目や耳が誰かのものに変わっているとは感じてきましたが、ことここにいたっては、直美の本来性に期待するより外はありませんでした。
告訴がとり下げられれば、それは直美の力が及んだものとして、将来への希望にまだ脈がある証(あかし)にいたしたいと祈っていました。かりにも、期待のはずれることがあれば、その時は、私は一大決意に立たなければならないと覚悟していました。
ともかく、第一回の公判の日まで待とうと、期待の胸に掌をあてていました。
第一回の公判は(昭和57年)三月三十一日で、この日は母(出口すみこ二代教主。昭和27年3月31日昇天)の三十年祭の日でもありました。私は大阪の市大病院のお世話になっていて、遥拝でおつとめをさせていただきつつ、在天の母に、いまの教団の大きな悩みについて、ひたすらにお詫びとご守護をお願いいたしました。
にもかかわらずこの日、公判はとりおこなわれたといいます。そればかりでなく、原告が裁判長に訴えたという言葉を伝え聞いては、私は唖然(あぜん)とせざるをえませんでした。
これではもう駄目だ!
つぎの日の卯月(うづき)朔日(ついたち)(昭和57年4月1日)、私が母のあとを継いで満三十年の日、これ以上、直美に期待をかけることはできない。今のうちに後継者のことをハッキリさせておかないと、大本はたいへんなことになると決意いたしました。
念のため、教主継承者の取り消しと、新任への二通の遺言状をしたため、しかるべきところにあずけることにしました。
さきにも申しましたように、直美の本来は、四代を継ぐべき性格を立派にいただいていますが、いまでは、それをまわりのものにふさがれて、どうにもならないところまできています。
この私の悩みを、のばしのばして今日まできましたが、ついに、のぞみを断たねばならなくなりました。
ことここに至っては、神さまの摂理によるところと思う以外はありませんが、直美のやさしさをおもうと、私は直美にすまなくて、直美をこのようにした方々をうらみたいほどであります。
それらの方々は、神さま一筋に誠をつくしてきたと信じられているので、教団の将来についてもっともだいじな直美をあやまらせてしまったとは気づかれていないでしょう。
勝海舟が西南の役(えき)にはてた西郷南洲をかなしみ、「自分には弟子のなかったことが幸いした」と言ったことが、いま身にしみるように分かる思いがいたします。
取り違いと慢心ほどこの世に恐(こわ)いものはありません。聖師さまが生きていてくだされば、このたびの私と同じことをなさったことでしょう。これは、誰よりも私が父のこころの動きを察することができたからハッキリと言えます。
父はいま、どれだけ残念におもい、嘆かれていますことか。
それにつけても、直美のことをとやかく中傷する人のあったこと、また私がこのたび直美のことを口にしないうちから、どういうわけかとり沙汰していたという人々のことを聞きますと、その心なき所作に、はげしいいきどおりをおぼえます。それらの人々はみずから深く省みなければなりません。
これまでも、この後も、直美は私の長女であり、親ごころにいささかの変わりはありません。私は、大本がだいじか、自分の娘がだいじかというところでは前者を主にいたしましたが、このたびのことで直美がどのように傷つくかとおもわないではいられません。それは、まさに断腸のおもいというものでしょう。
げんざいの直美に私の気持ちを伝えましても、直美の目と耳がもとに戻ってくれないかぎり、そのまま通じるとはおもえませんが、いましばらくはつらくても、ほんとうの仕合わせを見出だしてくれ、後ではかえってよかったと分かってくれることでしょう。私はその日の来るのを祈るばかりです。
ふつうの家の祖母であれば、私もこのまま娘や孫に負けてやりたいのですが、ここはそうはできないのです。
それは神さまに、教(おしえ)み祖(おや)(大本の歴代教主・教主補)に、この道の友にたいして申しわけが立ちません。こうした私の気持ちは、神諭(『大本神諭』)と霊界ものがたり(『霊界物語』)のこころに照らしてみてくだされば、なっとくしていただけると信じています。